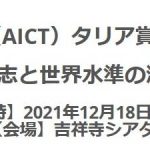小文字の他者を待ちながら―― 鈴木忠志『エレクトラ』『シンデレラ』における待機の位相/本橋哲也
だがここでの問題は、そのような「正しい斧」が本当に存在するのか、ということである。まずそれを傍証するのは、「夢を追い払いたい」というクリテムネストラの願望だ。今回の舞台でクリテムネストラを演じた内藤千恵子は、この人物の、夢と現実、敵と味方、恐怖と自信、愛情と憎悪、排除と依存の共存を、即座に千変万化する表情と声音と仕草によって、驚くべき多層性をもって表現する。おそらく前作の『「からたち日記」由来』において腹話術を駆使するかのような講談師を演じた経験が生かされた結果でもあるだろうが、彼女のクリテムネストラは二重人格どころか、その根源的な多重人格性によって、エレクトラの〈待望/耐乏〉がクリテムネストラの「絶望/希望」でもあることを如実に示唆する。クリテムネストラの独裁性を示す決定的な言葉――「この世に本当も嘘もないよ。あるのは私にとって嬉しいことと、私にとって嬉しくないことのふたつだけさ」――も、政治的な絶対権力者の妄言であると同時に、外部のない「病院」と化した現代世界においては、客観的事実よりも主観的認識が優先するというメディア支配社会の深層を言い当てるものとして聞こえるだろう。この言葉は最近、トランプ、安倍、プーチンといった、いわゆるポピュリスト政治家たちが多用したことで耳目を集めるようになった「ポスト・トゥルース」という言説の端的な例とも言える。「ポスト・トゥルース」とは、単に事実ではなく虚偽を言う、ということではない。事実とは異なることが仮にわかっていたとしても、自分の見たいもの、信じたいもの、自分にとって都合のいいことだけを言い立てるのが、「ポスト・トゥルース」の常道なのだ。それは精神分析で言う「否認」の一形態であって、事実を知らないわけではなく、むしろ事実を良く知っているからこそ、それを否定しようとする衝動や強迫観念に基づく。権力者は反復や韜晦、歪曲や転倒といった手段によって、事実と虚偽との対立そのものを無効にしてしまうような新たな言説空間を捏造することによって、「ポスト・トゥルース」世界に安住しようとする。そのために彼ら彼女らは表立ってなるべく饒舌であるほうがよく、言葉を選ぶ慎重さよりは思いつきを並べたてる軽薄さの方が人気を高めることになるのだ。
『エレクトラ』におけるクリテムネストラの饒舌は、内藤のカメレオン的な演技によって、正気と狂気、ユーモアとペーソス、諧謔と苦悩、女性と男性、親と子、主人と召使といった二項対立を易々と超えてしまう。オレステスの帰還を想像した彼女は、とつぜん童謡『ふたあつ』(作詞まどみちお、作曲山口保治)を口ずさむ。その三番の歌詞は、次のようだ――
まだまだ いいもの なんでしょか
まあるい あれよ かあさんの
おっぱい ほらね ふたつでしょ
エレクトラにとっては、父親を殺害した「正しい斧」が真実の証しであるとすれば、クリテムネストラにとっては「ふたつのおっぱい」が我が子オレステスとの血縁を保証する象徴なのだ。そして、この「斧」と「おっぱい」とが出会う時、その時こそエレクトラの待機が終わり、クリテムネストラの夢が追い払われ、家父長制度が復興するのである。

このような自らの存在証明をめぐる主人公たちの難問は次のようなクリソテミスの言葉によっても例証される――「今日のことが、本当にあったのかどうかも、分からない。わたしはわたしのことが、分からない」。このような記憶とアイデンティティ、現実と妄想、存在と認識との混乱は、クリソテミスが聴いた/見た/信じたというオレステス死亡の報告にも見て取れる――
オレステスが死んだのよ。ここから十日もかかる遠いところで、ゴツゴツと岩だらけの道で、乗っていた馬から落ちてずーっと引きずられていったんですって。
このように待機という現実と妄想との境界を侵犯せずにはおかない精神の有様は、ついにその対象とされていたオレステス(石川治雄)の登場によって危機に瀕する。上記のクリソテミスの報告の直後に、医者(プリハディ、塩原充知)によって車椅子に載せられて登場したオレステス――彼が実在の弟なのか、それともエレクトラの過剰な待望/耐乏が生み出した幻想なのかはわからない。精神分析によって人間の認識の位相を哲学的に考察したラカンによれば、人は一方で決して到達できない象徴界の大文字の他者につねにすでに憧れながら、他方で「想像界」「象徴界」「現実界」の中間にあって、自己にとって疎遠な他人の一部でありながら、自らが自己規定する際の根拠ともなる小文字の他者(「対象a」)を抱えて生きている。『エレクトラ』における大文字の他者は「お父さん」であり、小文字の他者は「オレステス」である。そのことを例証するかのように、エレクトラがオレステスに対面して、最初に直面するのは自己自身の鏡像なのだ――
エレクトラ お前の目にはこの私はどう映ってるの? … きっとびっくりしてるわよね… がっかりした? ぞっとした?
オレステスというエレクトラが待望していた小文字の他者は、結局エレクトラの自画像だったのではないか? そのような過剰な自意識の噴出を断裂させると同時に反復するようにして、エレクトラは「わたしの姿を見て」と懇願するが、エレクトラ/オレステス/医者が中央に一直線に並んだ舞台の構造は、この内面のドラマが分身による反復脅迫の衝動に依っていることを明示する。とすれば、続く姉弟の自己反復的対話も会話ではありえず、ベケット的な「欲望の反映でも、欲望の挫折がもたらす内面的感情の表出でもなく、すべてが自分自身にのみ語りかける」独白となるのだ――
オレステス この行いを許された者は幸いだ。
エレクトラ 自己の行いに至る者は幸いだ。
オレステス それを行う為に来た者は幸いだ。
エレクトラ 彼を待ち焦がれる者は幸いだ。
反復される価値判断の形容詞「幸い」が認識論の優位を示し、主語の存在論を相対化する。存在と認識とが最終的に合致するために必要なのは、上のような同語反復によって証明されようとする主語と述語の同一ではなく、目的語の認知である。そしてこの場合の目的語は何か、というとそれは、「正しい斧」という、「お父さん」の存在を消滅させた、架空で仮想の形象に他なるまい――
エレクトラ 斧を渡せなかった!あの子に斧を渡すのを忘れた!オレステスは行ってしまったのに、斧を渡すことができなかった!
「正しい生けにえの血が、正しい斧によって流され」ないと、クリテムネストラの悪夢も、クリソテミスの閉塞も、そしてエレクトラの待機も終わらない。エレクトラは斧を渡し忘れたのではなく、そもそも大文字の他者を消去する「斧」など、存在しようがないのである。

昨年までの『エレクトラ』上演では、エレクトラが最後に熱狂的な踊りを舞い、医者によって静かに舞台の外に連れ出された後で、高田みどりの打楽器の葬送曲に合わせて、五人のコロス、クリソテミス、オレステス、クリテムネストラが看護婦の押す車椅子に乗って、舞台奥上手から下手へと行進して終幕となる。ところが、今夏の上演では、その葬送行進が削除され、エレクトラの踊りの後、照明が一気に落とされて上演が終わる。認識論が存在論を凌駕する現代メディア社会においては、死者の哀悼や記憶さえも物象化されてしまうということだろうか? そこに絶望を読み取るかどうかは別として、確かなのは、舞台に一人残されたエレクトラの身体の強度だけが、今後も永遠に反復されていくであろう待機を支えるということだ。SCOT版『エレクトラ』がベケット的であるとすれば、それは神の不在と無意識と社会的下部構造という20世紀の課題を、永続する待機という一点に、俳優たちの強靭な身体が賭けられているからに他ならないからなのである。