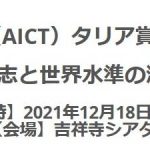小文字の他者を待ちながら―― 鈴木忠志『エレクトラ』『シンデレラ』における待機の位相/本橋哲也
ここで議論をもう一度整理しよう。『シンデレラ』の劇中劇的仕掛けは、あらゆる登場人物が俳優の本人とその役柄という二重構造のなかにあることを提示するのだが、そのような〈分身〉の構図は、演じ見られる側にある女優たちを舞台の上手半分に配置するというジェンダー的な分割によって、さらに強化されている。つまり、ニセ王子や父親役を女優が演じることで、分身構造が明快になると同時に、見る側と見られる側という安定した構造がズラされるのだ。下手側の男性制作者たちがSCOTの俳優と『シンデレラ』の役柄という二重構造のうちにいるとすれば、上手側の女性俳優たちは、SCOTの俳優と『シンデレラ』の役柄と偽物・本物を演じている存在という三重構造のうちにあるからだ。分身というモチーフをめぐって、男たちは一層構造、女たちは多層構造のなかに置かれていると言ってもいい。(舞台冒頭に登場したサチの父親によって喚起されているように、観客もその多層構造に巻き込まれている。)
そもそもジェンダーという社会的な性別分類などと言われる概念が、ひとりの人間の多層で曖昧でさまざまな性的欲望や可変的な性的ありさまを、便宜的に男女に判別した範疇であり、〈分身〉という人間に不可避の認識論的構造を隠蔽する方便に過ぎないのではないか。そう考えれば、『シンデレラ』という一見ジェンダー分割によって整然と制御されているかに見える舞台が、実は男たちのコントロールを超えて女たちが暴走するドラマであることがわかってくる。「ニセの王子」は「理想の妻を求めよ」という家父長(「本物の王子」の父親である王)の至上命令をコケにして、シンデレラの父親を騙すのであるし、その父親役を演じている女優が自らの家父長的権威を強調すればするほど、家父長制度の権勢なるものも見たいものだけを見て信じたいものだけを信じる「ポスト・トゥルース」の言説に過ぎないことが暴露される。そしてここで改めて強調しておかなくてはならないことは、このことを観客に如実に明らかにするのは、「ニセの王子」と「父親役」を演じている佐藤ジョンソンあきと齊藤真紀という、男と女、現実と虚構、身体と言葉、存在と非在、といった境界を途轍もない強度で侵犯してしまう女優たちである、ということだ。演劇の深層には〈分身〉というモチーフがあること、それを彼女たちのグロテスクにして崇高な演技は、驚嘆すべき集中力と密度によって明示するのである。
さらに私たちが誘われるのは、「本物の王子」と「シンデレラ/サチ」との関係を、「ニセの王子」と「父親役」および「姉役」「妹役」との関係との対比において考察することであり、そのとき重要となるのが〈待つ〉という契機である。嫁選びにやってきたニセ王子が「偽物」なのは、彼/彼女が高貴な家系の維持に必死な父親と娘二人に待望されていた存在であるからだ。『エレクトラ』の場合に倣って言えば、この場合の小文字の他者「対象a」は「ニセの王子」であり、大文字の他者は「本物の王子」である。よって、父親も姉も妹も、けっして「本物の王子」に到達することはないし、「ニセの王子」に出会い騙されたという幻想を反復するほかない。他方において、サチはニセであろうが本物であろうが「王子」など待望していない。この舞台でも、幻想の王子はあくまで「幻想」であって、その登場は2回とも中央舞台奥でスモークの雲に支えられ、スモークとともに雲散霧消する。サチは幻想の王子を演じる彼/彼女(進真理恵の静謐で浮世離れした存在感がここでの鍵となる)の存在など最後まで信じていないからこそ、シンデレラ物語の作者となることができているのだ。あくまで彼/彼女は、サチが毎夜書いている物語のなかの登場人物に過ぎないので、一回目は王子を追い払い、二回目は王子の呼びかけに対する応答を中断して、自らが書いた詩を独白することで幻想を断ち切る。そして何より(ロマンチックな男女の結びつきを期待する観客にとって)冷酷なことに、この劇は、サチによる待機の断念、つまり童話のハッピーエンドを最終的に否定する「王子様なんていないからね」という台詞によって終わるのだ。
『ゴドーを待ちながら』と同じように、ゴドーも王子もけっしてやってはこない。もしも『シンデレラ』という劇全体が、その劇中劇的構造も含めて、サチの書いている物語に過ぎないとすれば、「王子様なんていないからね」という彼女のあっけらかんとした声明は、劇作家の自己否定であると同時に、西洋近代リアリズム演劇の終焉を画した『ゴドーを待ちながら』をも、葬り去ろうとする「ポスト・ポスト・リアリズム演劇」を指し示すものなのだろうか? この問いの答えは、おそらくその言葉を聞いた衣裳スタッフ満田の諦念とも認可ともつかない、微妙に影をはらんだ微笑みに探すほかないだろう。かつて少女時代にシンデレラを夢見た彼女たちが、王子など決してやってこないことを知りながら、それでも待ち続けるのか、それとも待望を最終的に断念するのか、それは私たち自身に託された問いでもあるだろう。『シンデレラ』は、サチがフランスのシャンソン歌手アダモに自作の詩を提供して名声を得ている、という少女の自立の承認を経て、その歌が流れる中、舞台装置が片付けられて終わる。最後に残るのは、俳優である杉本幸と、SCOTのスタッフである照明の丹羽誠と音響の小林淳哉、それに衣裳の満田年水だけだ。かくしてこの劇は、作家とスタッフだけを残して、つまり演劇にとって必須の要素である俳優たちを消去した「非演劇」として終結するのである。
しかし、ここであらためて忘れてはならないことは、このような演劇を空洞化する非演劇、あるいは童話へのアンチテーゼとしての反童話、あるいは『ゴドーなんて待たないからね』とも名付けられるべき『シンデレラ』という演劇が、結局は、SCOTの俳優たちの強靭な身体性によって支えられているからこそ可能となっている、という事実である。そこでは、シンデレラの姉たちのグロテスクな存在感が美醜やセクシュアリティをめぐる二項対立的な社会的基準を超越する怪奇で不気味な(アンキャニー)次元に到達し、ニセの王子の千変万化する衝撃的/笑劇的な様相はまるでクレタ島の嘘つき男のような「真正の偽者」ぶりを発揮する。また「スズキ・トレーニング・メソッド」による役者の鍛錬法や、父親役がシンデレラ役のサチのタイミングの悪さを訴える、「監督、こんなところで立たれては次の台詞言えません」といった発言も、スズキ・メソッド的発声法によってきわめて真剣に演じられることによって「パロディ」が実のところ鈴木演劇においては、言葉やしぐさの意味の一義性を突き抜けるような重みをもっていることが提示される。
このような二項対立の脱構築を如実に示すのが、ニセの王子と父親との「イタリア語」による掛け合いにおける翻訳の力学である。突然思いついたかのように演出家が「ここからはイタリアオペラ風でやってみようか。音楽はロッシーニのシンデレラだ!」と言って『ラ・チェネレントラ』がかかると、父親役とニセの王子役の俳優が高速でイタリア語歌唱を披露し、その脇で紙芝居風の相当に割愛された、いい加減な「字幕」が展示される。佐藤ジョンソンあきと齊藤真紀という、「スズキ・トレーニング・メソッド」が身体の奥底にまで浸透した二人の俳優が、半音階進行の腹式呼吸発声法で、それとは真逆とも言うべき全音階進行のロッシーニの曲に合わせて、ベルカントのイタリア語で歌うというグロテスクにしてサブライムの極致。この不整合に観客はあっけにとられてしまうのだが、笑いながらも私たちは翻訳の政治学に気づかされる。「パロディ」と「真正さ」との境界が曖昧となると同時に、言葉の意味内容(シニフィエ)が言葉という記号(シニフィアン)に侵犯されることで、国民国家言語間の翻訳において、いかに恣意性が優先されてしまうかが暴かれるのだ。翻訳とは実のところ、シニフィアン間の置き換えに過ぎないのだが、それをシニフィエ間の意味の通訳と思いこむことによって、あらゆる翻訳行為は成立している。よって、この「日本語訛り」でありながら見事に「イタリア語らしい」無国籍言語をロッシーニ独特の軽快な音楽に乗せられて聴いてしまう観客は、自らの言語能力の無根拠性を問われるような自虐的な笑いに溺れる。さらに演出家はまたしても突然に「そこから日本語!」と宣言、ロッシーニの曲が速すぎて馴染むはずのない日本語、しかも日常では話されることのない「スズキ・トレーニング・メソッド」による特殊な日本語での歌唱が続き、今度は自らの「母語」のほうが「外国語」よりも理解しやすいという私たちの常識の根拠の不確定性が暴かれてしまうのだ。通常、翻訳は「日本語」「イタリア語」といった国境や民族といった「想像の共同体」同士の意味通約性を前提とした「国民国家言語」間で行われると考えられているが、実のところ、そうした異文化交通の可能性は、記号運用の恣意性や言語イメージの豊かさがもたらす意味の不確定性という効果によって支えられている。そして、そのことを明らかにするには、言語記号の意味ではなく、言語記号の形式そのものである音を国民国家言語の種別に関わらず只管(ひたすら)に発声できる俳優たちの怪奇で崇高な身体が必要なのだ。かくして『シンデレラ』という劇は、鈴木演劇の特質である堅固で明晰な空間構築を基礎として、ジェンダーの分割を顕在化させる外見の下に、登場人物たちの幻想と現実、過去と現在、実体と影、本物と偽物といった二項対立を〈待機の断念〉という契機によって解体するのである。
*
鈴木忠志がSCOTの俳優たちと共に半世紀近くにわたって利賀という日本の寒村で創造してきたドラマトゥルギー。その中核には<待つ>という契機、すなわち西洋近代リアリズム演劇を根底から批判する精神と肉体の営みがある。ゴドーもオレステスも王子も決してやってくることがないことが明白となった現代において、「ポスト・トゥルース」言説や家父長主義に退行することなく、演劇という身体的試みに賭けること――SCOTが『エレクトラ』のような精神分析的悲劇や、『シンデレラ』のような大人のファンタジーを上演し続ける意義もそこにある。
★本稿内の台詞の引用は全てSCOT提供の上演台本によります。また舞台写真もSCOTから提供していただきました。便宜を図っていただきました制作の重政良恵さまにこの場を借りて感謝申し上げます。