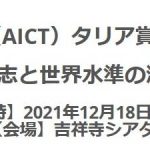小文字の他者を待ちながら―― 鈴木忠志『エレクトラ』『シンデレラ』における待機の位相/本橋哲也
一.『エレクトラ』における待機の永続
2022年の「SCOTサマー・シーズン」のオープニングを飾ったのは、ソフォクレスの原作にホーフマンスタールの「精神分析的な」視点が付加された脚本を、鈴木忠志が翻案したSCOT版『エレクトラ』である。昨年もインドネシア版でエレクトラを演じたアンディニ・プトゥリ・レスタリが主役を務めて8月26日に新利賀山房で開幕、その後28日にふたたび彼女がエレクトラを演じた後、9月2日からは佐藤ジョンソンあきがエレクトラ役となって、9月11日の最終公演まで同山房で4回の公演が行われた。You Tubeで舞台の録画映像を見ることのできる昨年のインドネシア版では、クリテムネストラを齊藤真紀が、看護婦を日本人俳優が演じた以外は、すべてインドネシア出身の俳優で演じられ、劇場は新利賀山房よりも舞台が広い利賀大山房であった。今夏の上演は、最初の2回でエレクトラと医者(バンバン・プリハディ)をインドネシアの俳優が演じたほかは、すべてSCOTの俳優によって演じられており、新利賀山房のより緊縮した空間もあって、きわめて緊迫した舞台が生み出されていた。以下、そこでの切迫感の由来を、本稿の主題である待機という契機に関連して考察していきたい。
鈴木忠志の演劇には車椅子が頻繁に登場するが、それは移動手段というよりも、他の場所への移動が許されない閉鎖空間における運動性の拒絶と超絶という矛盾した両側面を孕むがゆえに、SCOT独特のグロテスクで滑稽な動作や極度に緊張した身体表現が可能となる。それを「世界は病院である」という鈴木の思想と照合すれば、病院とは外部がない世界(というか、その外部には「死」しか存在しない世界)であり、そこを中心に描かれる舞台は完全に閉じられた共同体であって、外の社会、他者との交通空間が存在しないことによって狂気が育まれていく。つまり、この病院に収容されている登場人物たちは、体ではなく、狂気と正気との境がたえまなく侵犯されるような病気に罹っている。そのとき車椅子は、身体能力を持つが故にそれが「障害」となる者たちの病を抑え込み、病院という世界に幽閉しながらも、同時に身体的な解放をもたらす機械となるのだ。『エレクトラ』の冒頭に登場して「足踏み病」とでも言うべき崇高(サブライム)で怪奇(グロテスク)な反復脅迫を病んでいるコロス(植田大介、平野雄一郎、飯塚佑樹、江田健太郎、守屋慶二)の車椅子を高速で操り、柱の間をすり抜けて滑走しては急停車する超絶的な技巧。エレクトラの車椅子に拘束された閉塞とそこから解放されて空間を切り裂く舞踏の集中力との対照。クリソテミス(鬼頭理沙)による車椅子への依存と外界への憧憬。車椅子に屹立しながらそれに支配されているクリテムネストラ(内藤千恵子)の不安と焦燥。これらはいずれも、車椅子という、国家や社会の通常の枠組みの範囲内では自らの足で移動することが困難な身体を持った「障碍者」のための医療機械が、超絶的な身体能力と、言語の意味作用を無効にしてしまう非常識な発話との極端な共存によって、国家や権力の形成や中心化を妨げるような横断的なネットワークを創造する「戦争機械」(ドゥルーズ=ガタリ)へと変成された兆候なのである。
『エレクトラ』におけるこのような車椅子の革命的な反権力性は、運動性の化身であると同時に病院という世界の閉鎖性を体現したコロスが、通常のギリシャ悲劇におけるように距離を置いた観察者であるというよりは、エレクトラの内心の声を発話する分身であるというこの劇の構造によって、女性主人公の待望を表明する媒体ともなるという事実からも見てとれる。最初、医者によって車椅子に載せられて運ばれてきたエレクトラは、そこから降りても、ほとんど距離的な移動をすることがない。彼女は母親クリテムネストラによる父親アガメムノン殺害に起因する凄まじい精神的葛藤を内に抱えているがゆえに移動できず(現実的な文脈では、母親と継父のアイギストスの監視のもとで家の外に出ることが許されていないからでもあるが)、またあまりに多くの言葉を語る欲望に衝かれているために具体的な発声とならない。エレクトラを演じるレスタリと佐藤の凝縮された動物性エネルギーが満ちた身体と集中力は、重力の法則を無効としながら、クイックモーションとストップモーションを同時に行うような動作によって、正気と狂気、生と死、人間と機械の境界を侵していく。そんな彼女が、ただ一つ、人間としての、娘としての肉声を発露するのが、亡き父アガメムノンの名を呼ぶ瞬間である。『エレクトラ』という演劇のもう一人の主役が、アジア各地の伝統的な打楽器を駆使しながら、エレクトラの道行きに伴走する作曲・演奏の高田みどりであることは自明だが、エレクトラがアガメムノンの名前を叫ぶ場面で、高田が奏でる弦楽器「ウォータフォン」の音色の美しさは比類がなく、エレクトラの待望を絶妙に表現する。

構成・演出:鈴木忠志、音楽:高田みどり
新利賀山房
さらに注目すべきなのは、多くの思想家や精神分析者が注目してきたエレクトラという娘の父親アガメムノンへの郷愁が、この舞台では、彼女の言葉にならない内声がコロスというメディアによって媒介され分有されることによって、彼女の待望する父親の生霊の声となって、いわば夢幻能のような構造を形成していることである。つまりここにあるのは、身体と声の分割という存在論ではなく、聞いている意識と語っている意識の分離という認識論だ。よって、その父親の復讐を果たしたときに実現するであろう(と彼女が想像する)エレクトラの「踊り」なるものも、彼女の肉体という存在を焦点とするのではなく、そのまわりの風景を予見するという彼女独自の認知の証しとなる――
エレクトラ そしてすべてが思い通りに運んで、たくさんの血煙が空に向かって立ち昇り、それが太陽の光に映えて真っ赤なドームのようになって私たちを包んだら、そうしたら私たち、私と弟のオレステスはお父さんのお墓の周りを踊ります。
さらにここで決定的なことは、彼女が待望する父親による承認を果たしてくれる具体的な存在が、彼女自身の肉体ではなく、弟のオレステスであるということだ。「オレステスを待ちつつ」という卓抜な副題をみずからの作品の解説に付加した鈴木忠志の慧眼がここにあるのだが、そのことを時間のズレをはらんだ反復による待機の永続という視点から、さらに追求していこう。
まずこの劇では待機という契機がエレクトラにとどまらず、他の二人の女主人公にも伝染することによって、集団的な営為となっていることが注目されよう。エレクトラは弟が帰ってきて復讐を果たしてくれることを願い続けており(「オレステスはきっと来る、きっと帰ってくる、復讐をしてくれる!」)、クリソテミスは兄が死ぬことで閉塞状態から解放されることを望み続け(「いくら待ったって、だれも来はしないわ」)、クリテムネストラは息子に殺される夢に脅え続けている(「夢を追い払いたいんだよ。…… ねえ、お前、夢を追い払う方法を知ってるんだろ? 頼むよ、母さんに教えておくれよ!」)。まさに『ゴドーを待ちながら』と同様に、この三人が来ないかもしれないものを待ち続ける精神と身体の強度がドラマを駆動するのだが、『ゴドーを待ちながら』との明白な違いは、待たれていた、忘れられようとしていた、恐れていたオレステスが「現実に」家に戻ってくるということだ。その場面での姉弟の会話を検証する前に、この待機を支えている認識の構造をもう少し詳細に見てみる必要がある。まず、注意すべきは、エレクトラの待望を「希望」たらしめているのは、「斧」という具体的な存在だということだ――
エレクトラ 斧が、斧がある、血のついた、あいつらがお父さんを殺した、証拠の斧!
・・・・・・
正しい生けにえの血が、正しい斧によって流されれば、あなたはもう夢を見なくなるわ。