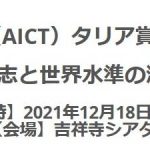小文字の他者を待ちながら―― 鈴木忠志『エレクトラ』『シンデレラ』における待機の位相/本橋哲也
はじめに
2022年夏の「SCOT サマー・シーズン2022」では、利賀フェスティバル40周年ということで、鈴木忠志構成・演出の3作品(『エレクトラ』『世界の果てからこんにちはI』『シンデレラ』)と、鈴木忠志、平田オリザ、中島諒人、宮城聰の4人がそれぞれ制作し若手の演出家4人(島貴之、早坂彩、伊藤全記、石神夏希)が演出した4作品(『紙風船』『新ハムレット』『胎内』『弱法師』)が上演された(「自然と共生する舞台芸術――世界の未来に向けて」)。演劇祭が始まる少し前の時期には、スズキ・トレーニング・メソッドの訓練に世界各国から多くの若者たちが集まり、感染症の影響でしばらく海外との交流が難しかった利賀にも、ようやく本来の賑やかさが戻ってきた。本稿の目的は、今夏の鈴木忠志による2作品の舞台を分析しながら、SCOT(Suzuki Company of Toga)のドラマトゥルギーの本質の一つではないかと筆者が推察する〈待機〉という主題について考察することである。半世紀近くをかけて築き上げられた「演劇の聖地」としての利賀という場所が、SCOTのメンバーたちの「動物性エネルギー」によって、生活という日常と演劇という仮構との独特な結合によって、稀有な時空間として出現する――その中核には、待つという特殊な営為があることを、今回上演された作品の検証をとおして明らかにしてみたい。
0.〈待つ〉とは、どういうことか?
今夏の演劇祭で上演された2作の考察に入る前に、まず仮説として、サミュエル・ベケットのドラマトゥルギーが鈴木忠志演劇の根底にあるのではないか、という問いを立ててみたい。ベケットは20世紀の西洋において「不条理演劇」の代表者の一人として、これまでの「西洋リアリズム演劇」とはまったく異なった戯曲の言葉と登場人物の造形、そして空間構成によって、演劇において西洋ヒューマニズム文明の終焉を告知した演劇人であった。近代西洋文明の批判にとどまらず、グローバルな規模で肥大した経済・政治・文化全般にわたる人間性の危機を20世紀後半から演劇によって摘出してきた鈴木忠志が、そのようなベケットのドラマトゥルギーに注目したのは当然とも言えるが、本稿では「待つ」という人間独自の行為を鍵として、鈴木演劇における身体的・空間的・心理的ありように迫る一助としてみたい。
「人間独自の行為」といま書いたが、それは人間の待機という営みが、人間以外の動物のそれと様相を異にするからだ。人間以外の動物も「待つ」が、それは本能的に、あるいは習慣として、待つ対象(それが自ら狙う獲物であれ、与えられる餌であれ、交尾すべき相手であれ、天候の変化であれ…)が必ずやってくることを知っているからだ。つまり、そこには確固とした存在への確信があり、そうした動物的営みの基礎には、自己と他者との厳然とした区別がある。しかし人間は、もう少し限定すれば「近代人は」と言うべきかもしれないが、そのような主体と客体、自己と他者、言葉と物との関係が、不安定となった時空間に生きている。神のような絶対的他者との厳然とした区別によって自己の存在が保証されていた時代が、はるかに過ぎ去ったことを、近代の末裔にいる20世紀以降の現代人は認知せざるを得なかった。その意味で、ベケットの演劇も、神は死んだと言ったニーチェ、心の深層を探ったフロイト、社会の下部構造に注目したマルクスに掉さしているのである。それを、存在論から認識論への転換と言っていいかもしれない。つまり、「何をwhat」という対象の実在性への依存ではなく、「どのようにしてhow」という身体の遂行性への信頼。他者へのまなざしではなく、自己の意識に重点が移動する――その時の鍵が、何を待っているかという存在への関心ではなく、待つという行為そのものの意味(ないしは無意味)への注目となるのである。
『ゴドーを待ちながら』や『しあわせな日々』が典型的だろうが、ベケット作品の主人公たちは、待つ、しかも誰も何もやってこないことを知りながら待ち続ける、という姿勢において際立っている。ヴラジーミルやエストラゴンやウィニーが西洋文明の末期的状況において、ひたすら何かを待つという姿勢に、大きな物語が終焉して以降の「ポスト」の論理を見ることは容易だろう。本稿が発想の出発点としているのも、鈴木演劇の根底にベケットと同様の現代の西洋文明に対する批判精神が胚胎しており、それを一貫して体現しているのが、主人公たちの身体が表明している待機の継続ではないかという問いである。
鈴木は多くの作品においてベケットからの引用を使っているが、ベケット作品そのものを上演したことはない。『ゴドーを待ちながら』についても、鈴木は著書の中でこの作品を現代不条理演劇の代表作として詳しく論じており、またそれを上演するのに最適な俳優たちをSCOTは擁していると思われるのにもかかわらず、主題としても形態としてもそれに近似した別役実作の『AとBと一人の女』は上演されていても、『ゴドーを待ちながら』は上演されていないのである。この理由を探るのが本稿の目的ではないが、ひとつのヒントは、鈴木演劇における外部の不在という点にあるかもしれない。
鈴木演劇における〈待機〉というテーマを考えるために、鈴木が『ゴドーを待ちながら』について論じている文章を、まずここで参照しよう。鈴木は、『ゴドーを待ちながら』においては、「人物の心理の展開や行動の変化があるわけではなく、待っていることの状態だけが浮き彫りにされて」くると述べて、ヴラジーミルとエストラゴンの会話を引用し、彼らの「会話」が相手に言われているというよりは自分自身に言われており、それは「意志する対象がはっきりわからなくなって、受身の意志とでもいうべき待つという行為、欲望する対象が出てくるのを待つことしかできなくなって」「本人たちが何を欲望しているのかわからない」からだと論じる。鈴木は続けて次のように述べる――
「内面の抑圧」とか「内面の分裂」とか「自己欺瞞」といった心理をあらわす言葉があります。これは、接触しようとする対象に向かって目的性をもって手段的に行動するときに起こる、さまざまな心理的軋轢のことですが、『ゴドーを待ちながら』の登場人物にはそうした心理的軋轢や葛藤がまったくありません。ただお喋りをして退屈をまぎらわせている。目的性がないために遊びになってしまうのです。言葉も行為も断片的で、論理的な整合性はありません。ですから、そこで語られる言葉は方向性をもっていません。欲望の反映でも、欲望の挫折がもたらす内面的感情の表出でもなく、すべてが自分自身にのみ語りかける遊びになってしまうのです。そこに最低の対象や方向があるとすれば、「待つ」という行為それ自体であって、言葉やしぐさはすべてこの状態を生きているという証し以外のなにものでもなくなっています。
(鈴木忠志『演劇とは何か』岩波新書、1988年、34頁。)
ここに明確に述べられているように、ヴラジーミルとエストラゴンにとって欲望の対象や言葉やしぐさに方向性がないということは、他者が不在だということである。ということはつまり、そうした他者の存在によって構築されたり規定されたりする自己の存在も空白であって、語るべき内面的感情や心理的葛藤もないということになる。鈴木忠志は『ゴドーを待ちながら』を上演してこなかったかもしれないが、ベケット演劇の根底にある、この他者や外部の不在という思想は正確に受け継いでいるのであって、それだからこそ、一方でベケット作品そのものを上演する必要はなく、また他方において、ギリシャ悲劇であろうが、シェイクスピアであろうが、チェーホフであろうが、長谷川伸であろうが、三島由紀夫であろうが、鈴木演劇は「ベケット的」になるのである。
鈴木演劇の登場人物たちには、外部や他者が存在しないので、自分の身体自体を「宿り木」や「病院」にするほかなく、そこに「狂気」が胚胎する。究極の他者である神の沈黙が問われ、宗教や信者団体への不信が語られる。舞台で頻繁に使われる歌謡曲やオペラは「女が男を待つ」というステレオタイプを反復する。「車椅子」の運動はけっして外部への通交とはならず、「籠」の男女はそこから抜け出せず、「廃車」の男は外に出ることが無い。流行歌や花火のような崇高でグロテスクな形象による物語の切断が、待つという契機を増幅させ、日常に隠された異次元的世界への跳躍を可能とする。つまり、鈴木演劇における普遍的なテーマとしての〈待望〉とは「耐乏」でもあるのだ。すなわち、待つことは、何らかの待たれる対象を必要とするが、その対象がはたして存在するのか、あるいは相手が自分の待機を知って応えてくれるのかがわからない、という中吊りの状態に耐えること、これが外部や他者の不在を前提とした鈴木演劇における待望という「希なる絶望」の様相なのである。
さて、このような待機の位相が、今夏の2作品ではどのように表象されていただろうか、それを作品ごとに検討していこう。