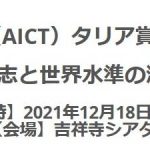日本への眼差し――ミシェル・ヴァイス

本稿はケベックの演劇批評誌『JEU』189号(2024年3月5日)に掲載されたMichel Vaïs « Regards sur le Japon »の翻訳である。ヴァイス氏と『JEU』編集部の許可のもと、『シアターアーツ』Web版のため片山幹生が翻訳した。
二年に一度行われる国際演劇評論家協会(AICT/IATC)の理事会が東京で開催され、私は幸運にも、能、文楽、歌舞伎、歌舞伎から派生した大衆的スペクタクルである大衆演劇、そして話芸のショーである落語など、日本の演劇のいくつかの側面に触れる機会を得ることができた。
能は、古くから続く壮大で荘厳な演劇であり、その上演時間は数時間にわたる。能の誕生後、数世紀のあいだに、能を土台とする他の演劇ジャンルが成立した。能の語り手は、喉から聞こえてくるような声で物語を語るが、実際にはその声は腹部の奥深くから放たれている。歌舞伎では能と同じ伝説(姫、君主、妖怪などが登場する)が題材として使われることもあるが、歌舞伎の演者は常に入念にコントロールされた歌唱的な発声を行う。文楽は大型の人形を使う演劇で、人形は顔を出した師匠と黒装束で顔を隠した助手たちによって操作される。ここでも、無言の登場人物である人形に代わって、語り手が物語を語る。これら3つのジャンルでは、語り手/歌い手、演奏者、操り手といった出演者はすべて男性である。
驚くべき日本のドラッグ・クイーンたち
私の友人が連れて行ってくれた大衆演劇は、200席ほどのささやかな劇場で、女装した男性俳優、「ドラッグ・クィーン」によって上演されるスペクタクルだった。スパンコール、羽根飾り、奇抜な衣装、大げさな演技、すべてがキャバレー・ショーを彷彿とさせたが、上演された演目の筋書きは先に見た文楽と同じだった。ショーの「演劇」パートが終わり、休憩を挟んで、一座は歌のショーを行った。スパンコールの衣装、ストロボ・ライト、レーザーは、「演劇」パートよりさらにキャバレーを彷彿とさせるものだった。トラック1台分はありそうなほど色とりどりの衣装が絶えず入れ替わった。
幕間に、役者たちが客席を回り、観客一人一人と握手をし、花が添えられたピン付きの封筒を得ることが目にとまった。休憩後の後半のショーでは、観客の何人かがひいきの役者を手招きして、身をかがめさせ、役者の衣装の胸元にお金や花が入った封筒を挟み込んだ。ほろ酔いの観客がダンサーの胸元やパンティに現金を入れるストリップ・ショーを連想させた。驚いて見ている私に、私を大衆演劇に連れてきた友人は、この一座は旅回りの公演を行う劇団の一つであり、一座の演者たち(俳優とダンサー)たちは家族・親族で構成されている(実際に4歳くらいの男の子がショーに出演していた)、そしてこの庶民的な演劇ジャンルには熱心なファンがいることを教えてくれた。実際、正午から午後4時まで続く約4時間の公演中、感動で涙を流す女性の観客が何人もいた。
語り芸のレビュー・ショー(寄席)では、舞台の中央に座り、ひとりで役柄を演じ分けて語る落語家とその他の演芸のパフォーマーが混在していた。手品師やスタンダップ・コメディのようなスタイルでマイクの前に立つコメディアン、表情豊かにコミカルに語る年配の女性の演者、そして最後に、白い厚紙から人物を切り抜く男性を見た。彼が舞台に手招きしたので、私は舞台でポーズをとった。二分ほどの時間で彼が私の似顔絵を切り抜き、私は大喝采のなか、それを受け取った。
利賀
しかし12日間の日本滞在のハイライトとなったのは、東京から600キロ以上、5時間かけて北上し、日本海に面しながらも海抜600メートルの山中にある利賀村にAICTの海外理事全員で行ったことだった。AICT日本センターの本橋哲也会長によるとこの村を「演劇のメッカ」と呼ぶ人たちもいるそうだが、私たちが利賀を訪問したのは、AICTが2021年5月の第29回大会(新型コロナのためオンラインでの開催だった)で、鈴木忠志氏に栄誉あるタリア賞(2006年以来8回目の受賞)を授与したのが主たる理由である。

鈴木忠志は、およそ50年前に自分の帝国(SCOT、Suzuki Company of Toga)を利賀村に築いた。鈴木は1976年に東京で活動していた自分の劇団を捨て、この貧しく隔絶された地域に移住した。冬には雪が降り積もり、藁葺き屋根の家々と伝統的な生活様式が残っていて、都会生活に魅了された住民たちにはうち捨てられた地域だった。徐々に世界中から彼のもとに男女を問わず若いアーティストたちが集まってきた。能にインスパイアされた厳しい訓練法を求めてやってきた彼らを鈴木は「同志」と呼んでいる。このカリスマに魅了された若者たちは、彼とともに土地を耕し、野菜や米を生産し、それを周辺地域で販売したり、配布したりすることを受け入れている。長い年月のあいだに、「同志」たちはSCOTの劇場やその他の施設も建設してきた。
大きさの異なる四つの劇場に加え、湖畔にある900人収容の壮麗な円形劇場を含む2つの野外劇場、稽古場、アトリエ、キャンプ場、食堂などがある人口400人のこの村で、鈴木は、夏と冬に数千人の観客を集める国際演劇祭を創始したほか、1972年にパリで開催された諸国民演劇祭(Festival du théâtre des Nations)以来、約30ヵ国で公演を行っている。彼は、能に着想を得た、身体と言語表現に基づく厳格な俳優訓練法「スズキ・メソッド」の創始者であり、このメソッドは数多くの国の演劇教育で採用されている。鈴木は現在までにギリシャ(1995年)、利賀、ロシア、中国、韓国、ハンガリー(2023年)などで9回開催されている演劇オリンピックの創始者のひとりでもある1)Voir l’article de Raymond Bertin dans Jeu 188.。


弟子たちが「鈴木先生」と呼んでやまない巨匠は、ときに皇帝のように威圧的にふるまう予測不可能なキャラクターとしてSCOTに君臨している。しかしその一方、トラクターに乗り、道を除雪する彼の姿もしばしば目にされている。84歳になる彼は、冬になると家の前を流れる小川に自ら飛び込んで「自分は2年後に死ぬんだ」と主張しているとのことだ。1995年からニューヨークのジュリアード音楽院でスズキ・メソッドを教えているアメリカ人、エレン・ローレンも彼の弟子の一人だ。彼女は30年前、20代で利賀にやってきて以来、定期的に通い続け、やがて鈴木のアソシエイト・アーティストとなり、世界各地で彼の主任アシスタント兼大使を務めている。師匠の話に戻ろう。ある日、頭を垂れている彼のスタッフ、俳優、研修生、弟子たちの一団を、鈴木が叱責している場面を私たちは目にした。しかし彼は、その様子を見ていた15人ほどの海外の演劇評論家たちの存在を気にも留めていなかった。
SCOTについては、『ディオニュソス』(エウリピデスの『バッカスの信女たち』に基づく)、『世界の果てからこんにちは』、『トロイアの女』の3つの公演を見ることができた。いずれも利賀や海外で長年にわたって上演されてきた作品である(『ディオニュソス』は1992年から上演されている)。そのため、この人気のある毎年恒例の祭典での上演には、「博物館的」かつ儀式的な側面がある。スペクタクルは利賀で生活する俳優たちによって演じられるが、彼らは俳優としての仕事だけでなく、観客の応対、食事のサービス、農作業も行う。重要なことだが、SCOTではチケットに定価はない。観客は払いたいだけの金額を払う。あるいは払わなくてもかまわない(しかし満席になることが多いため、事前の予約は不可欠だ)。ほとんどの人は一席あたり50ドル程度を支払うと聞いたが、学生たちが払う金額はこれよりはるかに少ない。あるいは無料で公演を見てもかまわないのである。
註
| 1. | ↑ | Voir l’article de Raymond Bertin dans Jeu 188. |