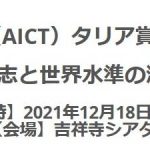日本への眼差し――ミシェル・ヴァイス
鈴木メソッド
利賀で聞いた話や私たちに渡された資料によると、鈴木は西洋の古典(エウリピデスやシェイクスピア)へのオマージュを排し、その翻案においては、むしろ物語や文脈を解体して、原典を変形させる。スタニスラフスキーのメソッドに基づくリアリズムを批判し、常に地面と接することを主張し、「足の文法」についての理論を発展させて独自の演技スタイルを生み出した。その結果、グロテスクにも崇高にも見えるものが立ち現れるということのようだ。鈴木はスタニスラフスキーのメソッドが生まれたモスクワ芸術劇場で『リア王』を2004年に上演した。
渡辺保『演出家 鈴木忠志 その思想と作品』(岩波書店、2019年)によれば、鈴木は「言葉と俳優の身体の関係」という「演劇の本質的な問題」を問うている。鈴木の演劇芸術は、「その普遍的な性格ゆえに、官能的で、美しく、猥雑で、グロテスクで、緻密で、残酷な方法で、現代の真実の姿や私たちが生きる世界の現実を提示し、人間のありようを映し出す演劇的な鏡を掲げている」と指摘する。鈴木にとって演技とは「語りの拒絶」であり、演じることは「語るのではなく、生きること」である(菅孝行『演劇で〈世界〉を変える―─鈴木忠志論』 航思社、2021年)。
普遍的な要素は、俳優の身体と演技の食い違いにある。「俳優が常に意識しなければならないことが4つある。重心、呼吸、発するエネルギー、そして声。俳優の技量は、安定した重心、呼吸による酸素の供給、エネルギーの消費、発する声、そしてこれらの演技のすべての側面への集中力をどれだけ身につけたかに比例すると考えている」(鈴木忠志、AICTタリア賞受賞スピーチ、2020年1月)。
自己表現力の一環として不動の状態を芸術的なやりかたで取り扱うには、集中力を最大限に高めることで強烈な存在感を生み出そうとする訓練が必要なのは言うまでもない。私は、エレン・ローレンが利賀で行ったスピーチ『見えない身体』から、以下のことばを書き留めた。「静止は誘惑の芸術であり」、「私たちの信念の力を可視化するものである。(中略)俳優の集中力は空間を刺激し、観客は日常を超えた何かを体験する。(中略)力を断ち切るようにして重心を安定させ、沈黙のなかで、正確に、深い呼吸を行わなければならない。(中略)話しているときに集中力を維持するのが一番難しい」、そして最後に「身体はあなたが表明することばを説明する」。
3つのスペクタクル
『ディオニュソス』(エウリピデスの『バッコスの信女たち』の読み替え)では、長い間、不動の状態で沈黙していたパフォーマーたちが、その後、身動きしないまま激しい自己表現を行う。それは「スズキ・メソッド」の分析をする人たちが言う「動物的エネルギー」を吹き込まれたかのようだった。臓腑から絞り出された彼らの声は、遠方から聞こえてくるようだった。パフォーマーたちは、能を演じているかのように、床の上を静かに滑るようにして移動する。強烈な照明によって、舞台美術は真っ白に照らし出されていた。字幕なしの日本語で上演されていたため、この舞台についてこれ以上語ることは難しい。

湖畔の円形劇場で上演された『世界の果てからこんにちは』は、はるかに祝祭的なスペクタクルだった。舞台は水上に設置され、舞台の両脇から斜めに二本の通路が延びている。この作品ではベケットの『カスカンド』や『勝負の終わり』、シェイクスピアの『マクベス』などの有名な戯曲の抜粋が用いられている。外国人観客に配布された解説文によると、この作品は自民族中心主義的な幻影であり、ある病院の人事管理部長と患者との間で交わされる食事についてのディアローグである。老人が黙って座っている間に、5人の仏教僧が自分たちの健康問題、つまり消化と睡眠の問題について語る。これは中心人物を精神分析しようとすることのメタファーとなっている。老人の歪んだナショナリズムは、知覚能力の低下によるものなのか、それとも破綻した国家への執着なのか。上演中に何回か花火が上がり、会場を明るく照らすことで、祝祭性に満ちた愉快な場面を盛り上げる。もうひとつの驚くべき趣向は、車椅子の俳優たちのパレードだ。俳優たちは、何度か歌いながら通路をリズミカルに移動する。完璧にシンクロさせた3秒ごとに片足を上げる彼らの動きは、驚くべき楽しい効果をもたらしていた。終演後に『世界の果てからこんにちは』によって、鈴木は自分が愛読していたいくつかのテクストへのオマージュとしてのスペクタクルを創造し、それによって現代のイメージを表現したかったのだと、説明されたのだが、私は狐につままれたような気分だった。カーテンコールのあと、鈴木先生がステージに上がり、花火に驚嘆した子供たちを連れた観客がいたことを嬉しく思うと言った。その後、彼はとある有名人である観客をステージに招き、日本酒が入った大きな二つの樽の蓋を一緒に割った。そしてその後、観客全員がステージに招かれてグラスを持った!

最後に見た『トロイアの女たち』は劇場での公演だったが、この作品はまた別の驚きを与えてくれるものだった。劇の中心となる人物はヘカベである。彼女の台詞が最も多い、驚くべき量の台詞だ。ヘカベは座ったまま、ハスキーで男性的な人間離れした声で、民族の死と避けられない終焉を嘆く。カサンドラや美しいヘレンは現れない。息子を悼みにやってきたアンドロマケとともに、劇中の場の大半を支配していたのは年老いたヘカベだった。その他の人物たちは、ほとんどの時間、動かずに無言の存在と化している。メネラウスも不在で、その代わりに彫像のように動かない人物がスパルタの権力を象徴している。ヘカベを演じた女優の見事な歌唱力は、相当な訓練の賜物であることは明らかだ。終演後に食堂でその女優に再会したのだが、そのときの彼女の声は柔らかく女性的なもので、舞台上での発声とはまったく異なるものだった!

今回の日本訪問(私にとっては2006年の2回に続き3回目)は、私を驚嘆させ、ときに困惑させるような体験となり、古くからの伝統とそれを今日まで受け継いできた実践と私は格闘した。スペースの都合で、私たち海外理事を招いて行われた能のワークショップや、家族で楽しむ縁日のような雰囲気のなか行われていた野外の落語フェスティバル、日本人の同僚たちとの温泉での忘れられない出会いについては、書くことができなかった。特に私の記憶に残っていることは、さまざまな形態の演劇が継続的に人気を博していたこと、観客の熱狂ぶり、舞台上でも客席でも着物の色彩が鮮やかだったこと、すなわち、演劇人とその歴史に愛着を持つ観客との交流のありかたである。