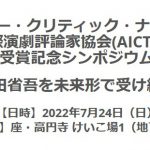「ナショナルなもの」を越えて〜『水の駅』(太田省吾作、シャンカル・ヴェンカテーシュワラン演出)/柴田隆子

撮影:守屋友樹
2016年秋、太田省吾の『水の駅』が京都芸術劇場春秋座で上演された。『水の駅』は太田率いる転形劇場で1981年に初演されて以来、国内外で高い評価を得て再演を重ねた「沈黙劇」の代表作だが、21世紀になってから国内ではほとんど上演されていない。今回上演を担ったのは、インドの演出家シャンカル・ヴェンカテーシュワランと、インド各地から集まったシアター・ルーツ&ウイングスの俳優たちである。
筆者はかつての転形劇場の『水の駅』を体験している。しかし演劇史に残る有名な舞台にもかかわらず、また一緒に行ったと言う友人らの証言はあるものの、どうもはっきりとした記憶がない。今回ヴェンカテーシュワランたちの舞台を観て、記憶の底に眠っていた『水の駅』を追体験することで、なぜ覚えていないのかその理由がわかったような気がした。この「沈黙劇」という実験は、数値化や標準化に対して感覚による異議申し立てを行う構造を持っており、かつての筆者はそれを見過ごしたのである。
「沈黙劇」がめざしたもの
太田省吾は、近代的なものの見方は本来多義的で豊かな人間という生命存在を抑圧しているとみなす。彼によれば、行動や言葉によって表現される西洋由来の近代演劇は人間や社会を要約し概念化して劇的に描くものである。そして今日の私たちがテンポの速い社会に対応するために行っている人生や社会で意味のない部分を削除して要約し概念化することは、この近代演劇的なものの見方に他ならない。フィクションである演劇が本来なすべきは、こうした要約を停止することである。そう考えた太田は、実生活の中で大部分を占める沈黙の時間に注目し、言葉を介在させず極端にゆっくりとしたテンポで動くことで、生命存在としての人間の領域を表現しようとした[1]。これが「沈黙劇」である。太田の論理は明快だ。だが、かつての筆者にはその意図が伝わってこなかった。それは舞台に散りばめられた構成要素の意味の束を瞬時に読み取ることとは真逆のことだったからだ。そこにすぐさま読み取れる意味など何もない。ではそこでは何が起こっていたのだろうか。ヴェンカテーシュワラン演出の『水の駅』を通して、まずは太田たちの試みについて考えてみたい。
時間感覚の変容
京都公演の舞台はほぼ忠実に太田の「記録としての台本」[2]を再現している。薄暗がりの中、水音が途切れることなく響く。舞台中央には水道の蛇口があり、そこから光る一筋の糸のように水が流れつづけ、水槽へと落ちていく。上手奥には投棄物の山、下手奥のスロープの上にはバスケットを持った少女がひとり。テクストには「歩いてくる」とあるが、その動きは動きと認識できないほど緩慢で微細である。舞台奥でごくごくゆっくりと変化する彼女の形状(フォルム)から、舞台を覆う暗がりが観客席の方に滲み出してくるようだ。尋常ならざるテンポに抗いながらも徐々に身体リズムが同調していく。頭を押し付けられるような意識の内省化。舞台が暗く感じられ、舞台を見ているのに見えていないような感覚とともに、時間が引き延ばされる。目は開けているのに見るべきものは何もない、ひどく長く感じられる時間。かつての私はこの退屈で意味のないように思われる時間に耐え切れなかったのだ。日常ではありえない高速は高揚感を増すが、その逆は意識が内面へ内面へと向かう。皮膚の表面で感覚的に意味の束を捉えるのではなく、腹の奥底で受け止めるものを探す感覚に近い。舞台にはなんの手がかりらしいものはなく、網膜に映る像への変化も感じられない。
ふっと絶え間なく響いていた水音が途切れ、またつながる。内に向かっていた意識が浮上していき、開いたままの目に赤い色が像を結ぶ。ゆっくりと差し出された少女の手の中にある赤、赤いコップだ。それから少し遅れて、水音と少女の行為の因果関係に思い至る。人間の<要約できない>領域を体感するための洗礼ともいえる時間体験である。

撮影:守屋友樹
こうした感覚変化を語るのは野暮だが、<チャクラが開いた>とごまかすのも違うような気がするので、少し説明をしておこう。不動産表示では徒歩1分を80メートルとするが、「沈黙劇」のテンポは2メートルを5分、つまり1分では40センチ、1.5秒でやっと1センチ進むスピードが基準である。通常の視覚情報処理ではこの変化は位置の移動としては認識せず、ほぼ同一とみなし見るべき対象から除外する。しかし、絶え間なく続いていた音が変化すると、その聴覚的変化の原因を視覚情報として探す意識が働く。見るべき対象としてそれまでなかった色がまず視野にマーキングされ、その形が認識され、そこで初めて少女のもつコップが蛇口の水を受けたために水音が途絶えたのだと、音とのつながりが了解される。こうして長々と書いたのは、普段は瞬時に理解する事柄を、この劇を観劇するスピードに身体感覚がなじむと、どの順番で自分が物事を意味づけしているのかに意識的になることが言いたかったためである。これは太田省吾と転形劇場の俳優たちが稽古の中で準備した構造だろう。
視線による空間拡張
続く蛇口を奪い合う二人の男の場面は、ゴミの山の前に座るこの少女の視線によってフォーカスされる。互いに求める水のみを見つめ、傍にいる相手の存在に気づかない、あるいは気づいても無視を決め込む男たち。奪い合いの末、接吻の態勢で互いを認識し、初めて男たちは相手を見合う。太田が記録したテクスト通りの行為が行われているのだが、男たちが「見合う」まで互いを見ないことが、いかに異様で、しかも私たちの日常の認識の仕方に近しいかが見て取れ、ぎょっとする。いや、ぎょっとしたのは私ではなく、舞台上の少女なのかもしれない。水への欲望が他者への束の間の欲望に変わる瞬間、少女は大きな目をさらに見開いたように見える。その彼女の視線が、舞台上のシーンに見入るこちらの視線に反射して、舞台空間を客席までぐっと広げてくる。水槽に注ぐ水音と薄暗がりに耳と目が慣れる頃、舞台を観る身体感覚は日常を離れ、舞台上の速度感を常態として感じ始めている。
シアター・ルーツ&ウイングスの俳優たちの目力は強い。[3]視線が他者を意識させ、視線が交わらないことでかえってその人間関係を浮き彫りにする。冒頭の男同士の接吻のように、水への欲望が他者への欲望に転化し、性と生が分かち難く結びついていることを示唆する場面は、この後に続く夫と妻の「交わらない目」による性の営みや、男と女のずぶ濡れで水槽からジャンプし抱きあうダイナミックな交歓にも見て取れ、興味深い。

撮影:守屋友樹
<他者>を見つめ直す機会として
水場を支点にして行きかう人々の行為や視線が、動きの速度を落とすことによって濃密になる。「列になって歩く」、「洗濯物を掲げる」、ただそれだけの行為が、かつて日本にあった戦後復興時の姿にも、国境を越えて移動する難民の姿にも見えてくる。これは観る側がもつ文脈による。舞台の解釈に正解はないのは言わずもがなだが、こうした連想が起きるのはなぜだろう。
実際には体験したことのない戦後復興や難民のイメージが舞台上の彼らに重なって見えるのは、舞台上の彼らが他者に見えていることに起因するのではないか。公共の場にある水道の蛇口から水を飲むという行為は、もはや<私たち>日本の都市生活者にとって日常ではない。荷物を持って移動する人たちは住所を持って暮らしている<私たち>とは違う。どこかそんな意識があるのではないか。難民や復興のイメージを重ねるのは、人とほとんど視線を合わせずに生きている日常の裏返しではないか。人を見ることを忘れ、欲望を隠蔽し、欲望の存在などなかったように生きている<私たち>の日常。では舞台上の彼らは他者なのだろうか。そもそも<私たち>と他者をどこで線引きをしているのだろうか。
動きと視線だけで綴られる舞台には、人間が人間を認識してその存在を認める時の意識の変化が明示される。人と人が向き合った時にしか生まれないであろう束の間の身体リズムの同調が、そこにはある。そしてそれは観客と俳優の間にも起こりうる。ちょうど冒頭の少女の視線に自己の視線が重なった瞬間のように。舞台上の身体に自分の意識を重ねながら、自分も含めた身体に他者を意識する、自己の身体の境界をゆさぶるような思考のあり方。上演中に劇場空間に満ちていたエネルギーが、それを続けるだけの胆力を演者だけでなく観客の個々の身体にも与えていたように感じた。

撮影:守屋友樹
「ナショナルなもの」を越えて
太田は「ナショナルなもの」が「思考停止点」となる可能性を指摘しており、言語もまた無自覚な前提としての「ナショナルなもの」となりうるという[4]。太田の言う「ナショナルなもの」は、換言すれば<私たち>を成立させる基盤となる共同体的なものの一部である。問題は共同体意識ではなく、無自覚に国家や仮想的集団に<私たち>を同定してしまう思考停止状態だろう。ヴェンカテーシュワランたちの舞台は、日本の文脈を離れても太田たちの「沈黙劇」の感覚実験が有効であることを示すものである。太田らの実験がますます速度感を増す日本の日常からはおろか演劇シーンからも忘れ去られようとしている中、別な文化的背景や演劇の歴史的経緯をもつ演出家と俳優たちによって演じられたことは注目しておいてもよいだろう。
「沈黙劇」は言語から逃れることができないことを前提に、いわゆる発話言語とは別次元に存在する演劇のコミュニケーションの実験を通して、思考停止状態を回避する試みである。世界的に言語は国家体制と必ずしも一致していない。ヴェンカテーシュワランたちの住むインドは広く、29ある州政府がそれぞれの公用語を定めるほど多彩な言語で知られる。インド・ケーララ州で国際演劇祭の芸術監督も務めるヴェンカテーシュワランが太田の「沈黙劇」の手法に注目したのは、字幕対応もできないほど多様な言語的背景をもつ観客を相手に上演プログラムを組まざるをえない必然から見出したものかもしれないが、むしろ異なる文化的、演劇的背景を持つ身体によって演じられることで、太田の意図がより明示的になったのではないだろうか。太田省吾たちの『水の駅』は稽古の中で醸造されたものであり、人間の<要約できない>領域を演じる目的からいってもテクストだけからではその精髄は読み取れない。彼らの舞台が太田の遺志を引継いでいるように見えるのは、転形劇場の俳優安藤朋子の協力があったからであり、彼女によるインドでのワークショップなどの積み重ねの結果でもある。[5]そして『水の駅』を「ナショナルなもの」を越えた取組みとして観ることができたことで初めて、筆者には太田の意図が身体的に腑に落ちたのである。
明白な敵や抑圧者が見えにくくなった今日、ヴェンカテーシュワランは太田省吾とハイナー・ミュラーを繋いで演劇による抵抗を試みようとしている。インド南部の有名な寺院と同じ名前を持つこの若き演出家は、2016年6月にドイツ・ミュンヘンで同地の俳優と共に「沈黙劇」の手法を一部に用いて『暗黒の日々 (Tage der Dunkelheit)』を上演し、[6]2017年5月には古代インド・マウリヤ朝の物語を元にした新作を上演するという。[7]
(11月13日16時の回 観劇)
[1] 太田省吾「日本の演劇における伝統と近代」『舞台芸術』13、2008年9月、4-8頁。
[2] 稽古に用いられた台本は、大雑把な行動の指示、詩や小説、戯曲、絵の引用を資料で示し、登場人物の行動や意識を間接的に限定したものであり、稽古のうちに資料の具体性は消えいく性質のものであったという。出版された『水の駅』のテクストは、稽古を経た行動の外面的記録「記録としての台本」であると太田は位置付けている。太田省吾『太田省吾劇テクスト集(全)』早川堂書房、2007年、233-258頁。以下、太田の「記録としての台本」からの引用は「 」で示すが、行動を示す言葉は頻出するため頁数は記さない。
[3]彼らの内の何人かは独特の目の動きで多彩な感情を表現するインド伝統舞踊の踊り手でもあり、ヴェンカテーシュワランの下でも目で演技することを稽古しているという。ムーン・ムーン・シン、ヴェヌーリ・ペレラ、アニルドゥ・ナーヤルからの聞き取りによる(2016年11月16日)。
[4] 太田省吾「思考停止点としてのナショナルなもの」『舞台芸術』3、2003年4月、1-4頁。
[5] インドでの『水の駅』初演に先駆けて2011年10月に安藤朋子によるワークショップが行われた。The Water Station. http://thewaterstation.tumblr.com/page/2
[6] Egbert Tholl, ‚Theater der Stille,’ Süddeutsche Zeitung, 2016.6.15. http://www.sueddeutsche.de/kultur/volkstheater-theater-der-stille-1.3035318
[7] Münchner Volkstheater. https://www.muenchner-volkstheater.de/spielplan/premieren/indika-ua