溢れ出る肉体――ダヴィデ・ヴォンパク『渇望』について/宮川 麻理子

1.序――カニバリズムというテーマ
ダヴィデ・ヴォンパク[1]振付による『渇望(原題:URGE)』は、2015年6月フランスのフェスティバル「モンペリエ・ダンス」で初演され、2016年3月に京都で来日公演を果たした。コンテンポラリーダンスの範疇は幅広いが、本公演は、およそ「ダンス」という言葉がもたらすイメージからはほど遠い。
人の背丈よりも高い、金銀に輝く屏風のような板が、半円形に舞台中央に立てられている。そこへ一人の男性が、黒いゴム素材のタンクトップに短パン姿で現れる。ぎょろりと目玉を剝いて、口元はくちゅくちゅと音を立てうごめいている。舌なめずりの音、舌鼓を打つような音、唸り声を発し、口の端からは涎がだらりと垂れ、ゴム素材の上着を滑って床にぽたりと落ちる。この開始早々の時点で、恐らく大多数の観客が抱いたのは嫌悪感というほかないであろう(事実モンペリエでの初演時、数人は足早に席を立ち退出した)。最前列に座ってしまった観客は、ダンサーがなるべく近づいてきませんように!と祈ったに違いない。だがこれは序章に過ぎない。
同じ素材の衣裳を来て、それぞれのやり方でお腹をすかせた野生動物のように口元を動かしながら、さらに三人のダンサー(ヴォンパク本人と女二人)が屏風の後ろから歩み出てくる。目を剥いて、時に不気味な笑みすらたたえ、ただただ欲望の涎を垂れ流していた彼らは、獲物を見つけたかのように、お互いの存在を自己の欲求の向かう先として狙いを定める。動物が縄張り争いをするように低い唸り声を挙げて互いに牽制し合ったり、女性二人がバトルでもするかのように、お互いの腹部を露出させ、それを飛び上がった勢いでぶつけてみたり、一人を羽交い締めにし、その目玉をまるでなめるように、あるいは鳥が嘴でついばむように食べるまねをしたり、彼らの肉体から発せられる欲望が徐々に爆発していく。
ここでは人間の三大欲求のうち食欲と性欲が、際立った形で表象されている。女性は胸を露出し始め、それを恍惚の表情を浮かべながら自分の手で揉んでいく。この行為は同時に、赤子に乳=食事を与えるものという二重の表象とも読み取れる。つまり、この女性の胸に顔を近づけ涎を垂らす男性ダンサーは、性と生という二重の欲求を持つことになる。いや、三重である。ここには(一応は)正常な欲求を超えた「異常さ」が透けて見える。それこそ、この作品の原点である「カニバリズム(食人)」というテーマである。作品全体を貫く極度の緊迫感は、私たちの世界では禁忌とされるこの第三の欲求に由来する。
ダンサーたちの体は、欲望に支配されつつ、どこかそれに抗うようにこわばり、引き裂かれた緊張状態に置かれている。相手(それは必ずしも異性とは限らない)の肉体に向かっていくとき、その衝動は率直には表現されず、まるでそれとは反対方向に働く筋肉の収縮があるかのように、異様な硬直が局所的に見られるのである。それは例えば、手先は他者をつかもうとしつつも、腕にはそれを抑制するような力が込められていたり、噛み付くことはできずに歯を食いしばって「涎」を垂らし続けるという表現に端的に現れている。「Urge」、すなわち駆り立てられるような欲動が溢れ出ることにより、肉体は統制や日常的な動作を乗り越えて、欲望を反映する衝動の塊となる。食人欲求とそれに抵抗する理性という内なる相克が、ダンサーの肉体の状態によって鮮やかに描き出されていく。私たちはここで、作品テーマであるカニバリズムの情景を舞台上に見出すことができるだろう。
2.領域の侵犯
しかしここで注目すべきは、この舞台で描かれた食人というテーマは単なる悪趣味的な趣向に留まるものではなく、人間の領土征服の欲望、具体的には植民地主義の問題をもその射程に収めているという点である。その意味でヴォンパクが創作にあたって重要なモチーフとしたのが、ブラジル人作家オズワルド・デ・アンドラーデの『食人宣言』であったことは無視できない。ヴォンパクは「植民地主義は一種のカニバリズムである」というアンドラーデの主張に共感している。ここでアンドラーデによって言及される食人とは、文字通り「人を喰らう」ことではなく、食人を行うように他者の領土を征服していく植民者というイメージと、その反転としてヨーロッパ文化をラテンアメリカが取り込んで=食べて、消化吸収し、新しい文化を生産していくイメージの双方を含んでいる。「食人という行為は、どちらか一方が他方を支配するのではなく、両方の要素が混合することで新たな生命を獲得する営みとしてとらえられる[2]」ものであり、植民地主義的な被支配の状況すらも飲み込んでしまう逆転の構造が見られるのである。したがって、ヴォンパクの舞台でダンサーが各々体現する他者へと向けられる欲求を、単に個人の食人欲求と捉えるのではなく、他者の侵略という植民地主義的欲望のメタファーとして読み解くこともできる。領土拡張の欲望のままに他者の身体へと侵略を進める様相は、暴力的で、あまりに不快な光景というほかない。涎を垂らし、相手の身体につかみかかり、お互いの手足にかぶりつこうとするさまはまるで地獄絵図である。ダンサーたちが提示するこれらの身振りが時に笑いを誘う滑稽さを醸し出している点を考慮に入れれば、他者の領域を侵犯する植民地主義への批判的眼差しも感じられよう。あるいは、「上品」「下品」という文化的コードすら破壊する身ぶり――男性器の一部を露出したり、三人が並んで四つん這いになり前にいる人の露出された尻部に顔をつけ、その横ではいわゆる半ケツ状態の男が鍛えられたジャンプのテクニックを駆使していたり――は、私たちの「常識」を凌駕し、社会規範を脱構築していくパフォーマンスとして捉えることもできるかもしれない。
同様にここでは、ダンサーたちの身体が舞台だけに留まらず様々な「感覚」を通して観客の身体へとなだれ込み、その支配を拡大していく、別次元での領域侵犯を指摘できる。「アーアー」というダンサーたちの歌とも叫びともつかない声が渦を巻くように重層的にこだまし、口から発せられるくちゅくちゅという音は否応なく耳に入る。そして涎という体液に代表されるような生理的反応が観客に感覚的な嫌悪を呼び起こすことで、単に見られる対象であったダンサーたちは観客の身体へと侵入していき、ここで支配と被支配を逆転する双方向的な欲望の交差が生じるのである。
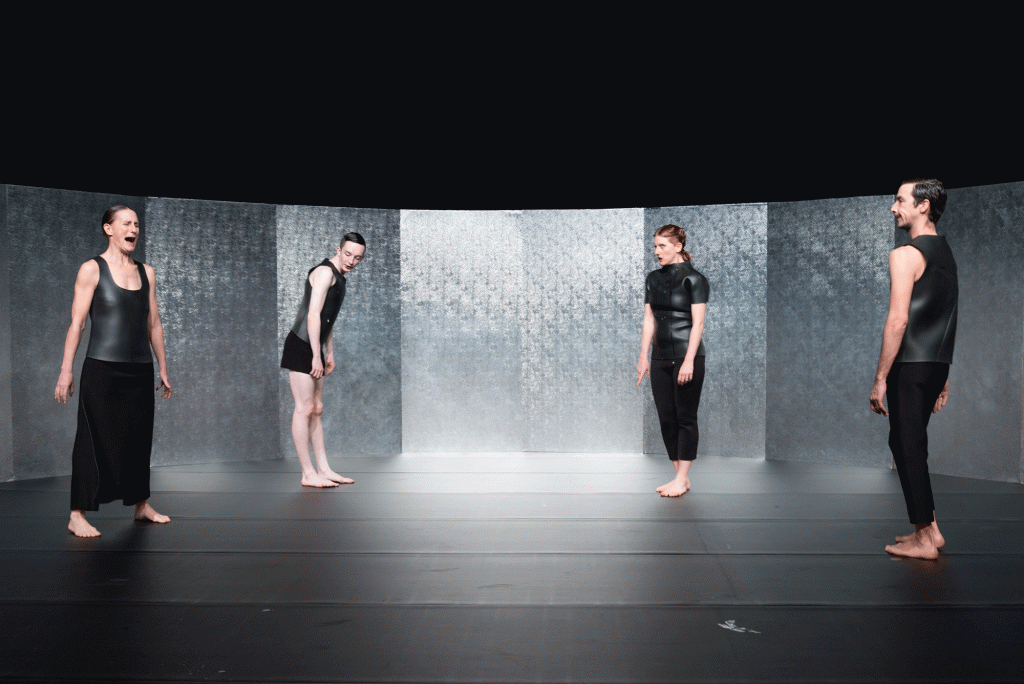
3.視線の暴力性
双方向性な欲望――視線がここで担う役割は重要である。第一に観客の眼差しは、「もっと過激なものを見たい」という欲望の現れである。しかしそうした実際の観客の視線とは別に、この舞台にはもう一つ重要な「目」が介在している。上演中、舞台で行われている四人のダンサーたちの行為を屏風の上からずっと見守っている二人の男女の存在である。彼らは同じように黒いゴム素材の長袖を纏い、最初は胸から上しか見えず、徐々に立ち上がっていくのだが、腰の辺りまで見えた段階で姿を引っ込めてしまう。ダンサーたちは時折この二人に対して、吠えかかったり、跳び上がってみたり、挑発的な行動をしてみせるが、二人は全く動じる様子がない。表情一つ変えずにダンサーたちを眺めているさまは、ある世界に注がれるもう一つの視線、つまり暴れる獣あるいは植民地主義の争いの現場をただ見ている創造者=神の視点であるようにも思われ、それはそのまま観客の置かれた立場にも重なってくる。事実、二人同様に観客も涎を垂らしたダンサーたちから強烈な視線で見つめられ、挑発される。見ている側の人間の代表として――その視線も実際は「過激なものを見たい」という欲望の現れに他ならないが――、この二人は舞台に居続ける。ただしヴォンパクは、この鑑賞者の視点すらもあざけりの対象に変えてしまう。ずっと下界を見下ろしていた二人は、途中一度引っ込むと、次に裸の尻を二つ並べて屏風の上手側の上部に突き出すのである。非常に滑稽で笑いを誘うこの場面は、見ている私たちの中にもダンサーたちが表象してきた欲求や、消化排泄というきれいとは言い難い機能が備わっていることを改めて突きつける。ヴォンパクの心地悪さと小気味よさは、観客の澄まし顔の裏側まで暴き出してしまうことにあるだろう。あるいは、さりげなく登場して笑いを誘うこの二つのお尻は、激しい領域の侵犯を繰り広げるダンサーたちの、そして植民地主義への嘲笑であるともいえよう。
そして最後に観客の欲望の視線は、強烈に裏切られることになる。幕切れの激しい音楽が鳴り響く中、ダンサーたちが去って無人の舞台が残される。このとき、屏風に極端に強い照明があたって強烈な照り返しが生じ、目を閉じていても感じられるほどの光が観客を襲う。この暴力的な明るさは、目という器官を通して観客の内へと拡張されるヴォンパクの世界であり、同時にダンサーたちに過激さを求める観客の欲望に対する切り返しであるといえるだろう。このラストで、双方がぶつかり合いスパークし、空の舞台に不思議と欲望の姿が浮かんでくるのである。
4.溢れ出る肉体――もう一つの創作の源泉
ところで舞踏を研究する筆者にとって驚きであったのは、ヴォンパクが本作の創造の源泉としてフランシス・ベーコンの絵画を用い、そこから「溢れ出る肉体」というアイディアを発展させていた点である。彼が参照した絵画〈砂丘(Dune de sable)〉には、赤い背景に、水色の景色が広がる窓のような穴があき、そこから肌色というよりは赤黒いどんよりとした肉が流れ出す様態――まさしく体という入れ物/絵画の画面から溢れ出て、領土を拡張していく肉体――が描かれている。この溢れ出る肉体のモチーフは、一般的な社会的枠組みから溢れ出す欲望の身体=カニバリズムの身体であると同時に、肉体は境界の定まった孤立した存在ではなく、そこから発せられる多様な要素(唾液や接触による他者の感知、呼吸など)によって拡張していく、流動的な存在として捉えることもできる。周囲のものと常に関係をもち、同時に外部からも影響を受けるこの「多孔質の身体[3]」は、まさにそのまま舞踏の身体ともつながるのである。舞踏の創始者土方巽も創造過程でベーコンからインスピレーションを得ていたのは非常に興味深い類似点である[4]。森下隆は、ベーコンの絵画に見られる「肉体の変形、歪曲、溶解、蒸発、気化といったさまざまな様相は土方の舞踏の特徴をよく表し、土方の世界そのものといってよい[5]」と述べている。物質的な肉体の境界を超越し、メタモルフォーゼしていく状態を目指した舞踏はむしろ、この領域の侵犯を積極的に受け入れ、あらたな肉体のあり方を模索したと言えるだろう。一方ヴォンパクは、フォルムそのものの変形よりも、様々な感覚器官を通して溢れ出る/拡張される肉体を探究したように思われる。そして上演中つばを吐き続けなければならないほど過酷な、体液までも総動員するこの表現は、筋肉・神経・感覚のすべてを意のままにできる身体表現のプロフェッショナルでなければ到底務まるものではない。外部へと開かれ、固定された領土としての身体からは脱しつつ、その身体全てを意識的にコントロールする能力が要請される点は、舞踏との類似の裏にある決定的な差異といえよう。いずれにしても、明らかに身体に立脚しながら拡張された「ダンサー」の範疇を提示したという点において、この作品は衝撃的であった。
欲望は、その極限にまで至って体の外へ流れ出して行く。ヴォンパクの振付は、その流れ出す欲望を体が持つあらゆるものを総動員して表象する。これは身体を自由に操ることをその是とするダンスの領域に(つまりダンスとは、もっと多くのものをその語彙の中に含んでいるものなのだ)最もふさわしい作品である。


[1] David Wampach。フランスを拠点に活動する振付家・ダンサー。2001年に演劇的アプローチと造形美術的アプローチを融合したスタイルを確立し、Association Achlesを結成。国内外のフェスティバルに招聘される。2011年にはレジデンスアーティストとして京都のヴィラ九条山に滞在し、ワークショップを行った。なお、名前の読みとしては「ダヴィッド・ヴァムパック」がフランス語の発音に近いと思われるが、ヴォンパク氏本人がアンスティチュ・フランセと協議の上「ダヴィデ・ヴォンパク」という表記を選択したとのことで、本論ではこの表記で統一した。
[2] 本橋哲也『ポストコロニアリズム』岩波書店、2005年、p.56。
[3] 舞踏と「多孔質の身体」については、Sylviane Pagès, Le butô en France――Malentendus et fascination, Centre national de la danse, Pantin, 2015, p. 128を参照した。
[4] ヴォンパクはリサーチのため京都に滞在した経験があり、また近年ではアングラ演劇の雄・寺山修司にも関心を持っているため、土方を参照した可能性もゼロではない。
[5] 森下隆『土方巽 舞踏譜の舞踏――記号の創造、方法の発見』慶應義塾大学アート・センター、2015年、p.97。
公演データ:『渇望(原題:Urge)』ダヴィデ・ヴォンパク振付・演出、初演2015年6月27−29日(観劇日28日22時)、Festival Montpellier Danse、Studio Bagouet, Agora/再演2016年3月5−7日(観劇日6日20時)、Kyoto Experiment京都国際舞台芸術祭2016 Spring、ロームシアター京都ノースホール




