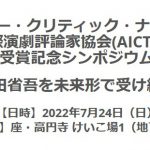幼女のまなざす水俣に触れて ―― 井上弘久独演『十六女郎 椿の海の記 第三章・第四章より』/新野守広
井上さんは、さらに年の離れた4歳の幼女も演じる。この幼女みっちんは、執筆当時40歳代だった石牟礼道子が幼少期の記憶を再構成して生み出した文学的形象である。幼女の目を通して、私たちは1930年代の水俣を見、その風土につながることができる。みっちんを演じるとき、井上さんの両目は大きく開かれ、顔面の様相が変わる。幼い娘を模倣しているのではない、ただならぬ気配が、井上さんのたたずまいにみなぎる。時と場所を越え、石牟礼のまなざしと私たちのまなざしをつなぐ媒介にならんとする気魄(きはく)であろうか。
みっちんのまなざす世界はすさまじい。作家の幼少期、道子の家には母方の祖母が同居していた。おもかさまと「さま」付けで呼ばれたこの祖母は、精神を病んでおり、風呂を嫌い髪もぼさぼさ。しかも盲目で頑なだったが、幼い道子とは不思議と心が通いあったようで、祖母に発作がおきると、相手をするのは道子の役目だった。こうした幼少期の体験を踏まえて、小説には老いた狂女と幼い孫娘との魂の触れ合いが描かれている。
たとえばみっちんがおもかさまの蓬髪(ほうはつ)を結う場面がある。井上さんはおもかさまとみっちんの方言でのやりとりを語り、髪を結い/結われる祖母と孫娘の所作を演じながら、標準語で書かれた地の文を語った。ときおり咳き込みながら、喉の奥から息を絞り出すように語られるおもかさまの声。好奇心旺盛で感受性の鋭い孫娘の柔らかくやや高い声。元結いを終えたみっちんはおもかさまの髷の両側にぺんぺん草を挿す。井上さんは小さな鈴を静かに鳴らす……「草の実の音の彼方に、人智のおよばぬ寂しい世界が漠々とひろがってゆく」(『椿の海の記』第4章「十六女郎」)。

(写真は2024年10月、水俣市南部もやい直しセンター「おれんじ館」での公演)
第4章「十六女郎」では殺人事件が語られる。女郎屋「末広」のぼんたと呼ばれた16歳の娘が近所の中学生に刺殺された。早朝、うわさを聞いて女郎屋の前に集まった町の人々のざわめく声を、井上さんは語り分ける。人々は、だれに聞いたのか、ぼんたの最後のひと声をうわさし合う。井上さんは静かに立つと、死んだぼんたに成り代わるように、その最後のひと声を小さく声に出す、「おっかさーん」。
最後の場面は、ぼんたの通夜代わりの酒席である。みっちんの父亀太郎が登場する。亀太郎は近所のよしみもあり、親戚代わりにぼんたの解剖に立ち会った。隣家の店で酒をふるまわれた亀太郎は、若い衆とともに深酒する。幼いみっちんも酒席に同席する。おなじ天草出身というだけの、縁もゆかりもない女郎の死を目の当たりにして、亀太郎は悔しさを吐露し、憤り、若い衆とともに号泣さえするのだ。町の人々から蔑まれた女郎たちの生活は現世の奈落であるが、みっちんの一家も奈落と無関係ではない。終生社会的弱者に寄り添った石牟礼道子の姿勢が鮮やかに示されている。井上さんは浄瑠璃太夫さながらに、亀太郎の悔しさと憤りを万感込めて語りあげる。
この章の最後に、酔った亀太郎が娘に声をかける場面がある、「ほら、みっちん、お父っつぁまにつげ。おまやけっして淫売のなんのにゃ売らんけん、しあわせぞ。いっぱいのめ、のむか、うん」。父に声をかけられた幼い「わたし」は、こっくりうなずいて、杯を受ける。父娘のやりとりには、執筆に先立って亡くなった父への作家の想いも込められていよう。
井上さんは客席に向かってひざまずき、両手を杯の形に合わせて胸の前に静かに掲げ、前方を見つめた。合わせた手は、蓮の花の蕾にも、小さな船にも見える。井上さんのみっちんが、いまそこにいる亡き父に向き合っているようにも思えて、終幕となった。
若き頃、老体をテーマに掲げた転形劇場に参加した井上さんが、老齢に達した今、幼女の目を通して、もう一度生を生き直している。その姿は、近代化に邁進した戦後日本に水俣の苦しみを突きつけた石牟礼文学の意義と魅力をあらためて私たちに伝えた。