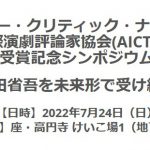幼女のまなざす水俣に触れて ―― 井上弘久独演『十六女郎 椿の海の記 第三章・第四章より』/新野守広
井上弘久氏の一人芝居である。井上さんは2010年春から2011年秋にかけて、かつて所属していた転形劇場の太田省吾三部作を上演した後、主宰していた劇団U・フィールドを解散して、ブコウスキーやカフカなどの作品のソロライブを始めた。2018年からは石牟礼道子の小説『椿の海の記』全11章の各章ごとの舞台化に力をそそぎ、2022年からはふたたび第1章に立ち返って水俣市をはじめ全国各地で一人芝居を上演して回っているという。
U・フィールド解散以後の活動について何も知らずにいた私は、偶然、独演『十六女郎 椿の海の記 第三章・第四章より』の公演情報を見つけた。会場は神奈川県藤沢市鵠沼海岸のミニシアター・シネコヤ。20名も入れば満席になる落ち着いた映画館である。久しぶりに見た舞台上の井上さんは、優しくユーモアに溢れるとともに、繊細で、力強く、私はその途切れぬ集中力に圧倒され、一挙手一投足に目が離せなかった。やや長くなるが、ここに私の見た井上さんの舞台を記してみたい。

原作=石牟礼道子
出演・構成・演出=井上弘久
作曲(不知火海のテーマ)=金子忍
2025年3月21日(金)~3月24日(月)/シネコヤ
撮影=高平雅由
(写真は2024年10月、水俣市南部もやい直しセンター「おれんじ館」での公演)
映画館のスクリーンと客席の間の狭い空間に椅子が1脚置かれている。白い足袋を履いた井上さんが赤い長袖シャツに半袖の薄衣姿で現れ、まず小半時間ほど作品について話す。そして、カリンバと呼ばれる小さな箱状の楽器を手に取ると、独演が始まる。ほかには小さな鈴を使うだけの、一人で語り、演じ、奏でる1時間半である。
『椿の海の記』は1976年に公刊された。作家石牟礼道子が幼少期を過ごした1930年代の水俣を、作者の分身である幼女の目を通して描いた自伝的小説である。この小説には、地の文(おもに標準語の書き言葉)と、「 」で括られた人物の言葉(方言)に加えて、周囲の物音や人々の声が地の文に書き込まれており、黙読していてもさまざまな音や声が聞こえ、幼い道子の目の前で人々が動き出すような臨場感がある。井上さんはこれらの言葉を性質や人物の特徴に基づいて語り分け、ときおり身振りもまじえて演じていく。自在な語り分けは、たとえば浄瑠璃のような語り物の伝統を感じさせたが、同時に、語られた言葉の背後に広大な時空間と堰き止められた熱いエネルギーを感じさせる井上さんのたたずまいは、転形劇場の無言劇を想い起こさせた。
『椿の海の記』第3章「往還道」は、1930年代当時の水俣市栄町が舞台である。栄町は、20世紀のはじめに不知火海に面する梅戸湾に新港が出来た際、市街地から道が開かれたのを機に沿道に出来た新興の町。道子の家は天草から水俣にやってきた石工の一家で、祖父の代に梅戸港への切通し工事も請け負い、天草出身の若い衆を住まわせていた。
1918年に水俣に新工場を建設した日本窒素肥料株式会社(現JNC)のために出来た港が梅戸港である。水俣病が公式発見(1956年)される以前の話であるが、新港につながる道を開いた一家に生まれた道子は、後年水俣病の患者たちの支援活動に尽力する。因縁の道というべきか。
早朝、まだ夜が明けきらぬ中、祖父たちが作った栄町の道の上を、漁村の女房たちが獲れたての魚を女籠(めご)に担いで走り抜ける。戦前日本の生活の息づかいが井上さんの全身から伝わってくる。カリンバのリズムにのって、魚売女房たちの踊るように駆ける足音と魚を売る声が響く。客席に座る私の心も躍る。しかしやがて、カリンバを弾く手は止まり、小説の語り手の厳しいコメントが低い声で語られ、打ちのめされる-「この女房たちの二代目、三代目がことごとく、後年水俣病になってゆくのである」。水俣の現実と正面から向き合った『苦海浄土』の作家は、一見牧歌的な幼少期の回想にも批評の眼を閉じない。
井上さんの語りは続く。栄町に女郎屋「末広」ができる。そこに売られてきた娘たちは、道子の家に寝泊まりする若い衆と同じ天草出身である。自分の姉妹や親戚や知り合いの娘たちが連れてこられているかもしれない。娘たちを想う若い衆たちの方言で書かれたやりとりを井上さんが語りだすと、彼らの切なさがひしひしと伝わってくる。
女郎たちが通う髪結い屋の場面も面白い。70歳を超えた井上さんが、元結いを締めてもらった若い娘の伏し目がちに遠慮する姿を、頬に赤みがさすように初々しく演じる。年の隔たりを越えて、老役者が若い娘を演じる姿は、独演の大きな魅力だ。