闘うセレネ――「マレビト」とは何者か?――金森穣『闘う舞踊団』・Noism0+Noism1『セレネ、あるいはマレビトの歌』/本橋哲也
本稿の目的は、金森穣著『闘う舞踊団』(夕書房、2023年1月)の書評と、金森穣演出振付、Noism0+Noism1『セレネ、あるいはマレビトの歌』(黒部前沢ガーデン、2023年5月20~21日)の舞台評とを合わせて執筆することで、この舞踊家にして、日本初で唯一の公立劇場専属舞踊団の芸術総監督の「闘い」について概観することにある。このように書評と舞台評とを、ひとつの拙文のなかで提出することで、単なる舞台評ではなく、金森穣という傑出したアーティストの軌跡と現状と展望を素描できるのではないかと考えている。以下、拙稿の構成も、書評と舞台評という二部からなる。
1.「地方から世界と勝負する」――『闘う舞踊団』
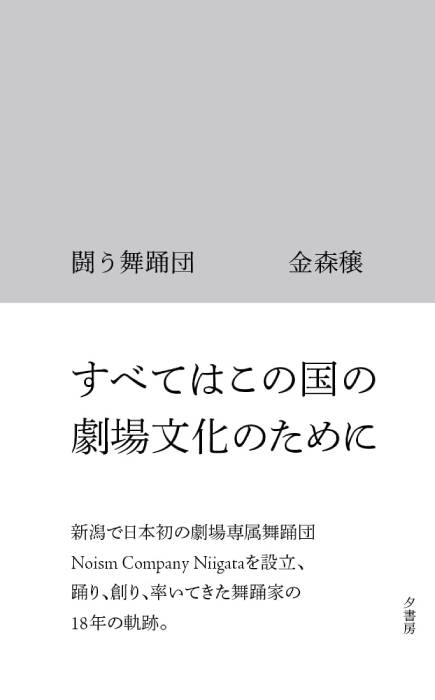
著=金森穣
夕書房 定価2200円(税抜)
金森穣は2004年4月から2022年8月まで、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館の舞踊部門芸術監督と専属舞踊団Noism芸術監督を兼任、2022年9月より、Noism Company Niigata芸術総監督を務めている舞踊家である。『闘う舞踊団』は、金森の舞踊家人生を語り下ろしたものだが、その中核には、日本といういまだに劇場文化が市民の中に根付いていない社会において、公立劇場が専属舞台芸術集団を持つことの意義に対する文化政治的な問いかけがある。「劇場専属舞踊団」とは、「劇場が一つの舞踊団を丸ごと抱えて、舞踊家やスタッフの給料や社会補償、日々の稽古・創作のための環境を提供し、その創作物を劇場から発信していく欧州の劇場文化システム」である。(『闘う舞踊団』、44-45頁)ここにも「欧州の」とあるように、舞台芸術が学校教育やさまざまなメディアを通して、日常生活の一部として浸透し、国民・住民・市民・訪問者に対する行政サービスを経済的組織的に支援する文化政策として定着しているヨーロッパとは違って、日本の劇場文化には、国民や市民の税金を使う文化政策として舞台芸術を育てるという発想も実践もきわめて乏しい。たとえば、日本では20世紀末の地方再興計画で莫大な税金が使われ、全国津々浦々に二千あまりの「公立文化施設」が作られたが、当時の地方自治法第244条で定められたように、それは「公の施設」であるから、住民の要求があれば貸し出さねばならず、専属の劇団なりが占有使用することはできない。つまり、それらはハードとしては「劇場」であるかもしれないが、ソフトとしては「貸会場」なのである。
2002年夏にヨーロッパの舞踊団の最前線で活躍していた金森は日本に帰国したが、日本の劇場文化の拙劣さに絶望して、日本を離れようと思っていた矢先、新潟市の公立劇場である「りゅーとぴあ」から芸術監督になってほしいという要請を受ける。しかし当時、金森が委嘱された「芸術監督」というのは、他の多くの「公立劇場」のそれがそうであるように、本拠地は東京に置きながら、東京で自分が創った作品を地方に呼んできたり、劇場の運営方針に助言をする役割に過ぎない。ここから金森の試行が始まるのだが、本書で何度も私たちは出会うことになるように、彼はきわめてしぶとく、肝の坐った人間で、危機を好機に代えるというか、「困難な状況に置かれた時にこそ人は真価が試される」という格言を証明するような人物なのである。
こうして金森による日本で初の(そしていまだに唯一の)劇場専属舞踊団を新潟市の公立劇場であるりゅーとぴあに作るという、長い旅路が始まることになる。まず彼が試みたのは、「プロ」と自他ともに認める舞踊家集団を地元に作ることだった。日本の舞台芸術界には「プロ」を測る基準がなく、結局、作品も演出家も俳優もダンサーもどれだけ「有名」かという「知名度主義」に依っている。だから、誰もが情けないと知りつつ、知名度のある俳優を連れてきて、ほとんどまともな稽古もせず、劇団としての結束力もないので、意識も演技スタイルもバラバラ、演出家のドラマトゥルギーも存在しない舞台が横行する。しかし、それでも有名なタレントが舞台に出れば客は入るので、「プロ」が育たないという悪循環が続くことになる。金森が自身の舞踊団に要求したのは、そうした悪循環を断ち切るための専門家としての意識と実践だった――
生活は保障するから、朝から晩まで鍛錬できる環境を作りたかった。舞踊家とは、この広く多様な社会において、人間とは何かという普遍的な問いを、その身を通して探求し続けている求道者のような存在であり、それゆえに社会的保障を必要としている専門家だという認識が私にはあるのだ。(同書、49頁)
このような専門家の欠如という問題に密接に結びついて、劇場文化の醸成を妨げているのが、日本における「劇場」の性格である。金森によれば、日本の劇場の大きな問題は、歴史的に劇場の前身が公会堂であり、今でも多くの住民や行政者が劇場を地域市民の利用に供する会館と捉えているからである。よって、劇場が芸術創造の場となるためには、専門家の参加が必要だ。金森の明快な区別に従えば――
市民会館という開かれた市民のための場と、劇場という開かれた専門家のための場。どちらも「開かれている」べきであることに変わりはないが、両者には大きな違いがある。市民会館が市民の利用、外部から来る様々な公演を市民に提供するといった「利用・提供」を目的とするのに対し、劇場とは専門家を抱え、専門家が日々の訓練をしながら、「舞台芸術」を創造し、世界に発信するという「創造・発信」が目的の場であるということである。(同書、57頁)
かくして、りゅーとぴあにおける専属舞踊団は出発するのだが、そこには新潟市の行政担当者である事業課長や当時の市長の理解と応援があった。このことは、日本における公立劇場の成功、不成功を考える時の鍵であり、また最大の問題点の一つでもある。行政にも数は少ないかもしれないが、舞台芸術を理解し、積極的に支援する人びとがいる。要はそのような人たちと出会えるかどうかが、多くの事例において、公立劇場の帰趨を決してきたのであり、逆に言えば、そのような人びとが行政の現場を離れてしまえば、たちまち劇場の運営は危機に陥るという致命的な弱点を日本の舞台芸術は抱えているのだ。ここで考えるべきは、行政と文化との関係である。日本の文化行政に今後求められるのは、「支援」ではなく「政策」であると、金森は言う。(同書、59頁)しかし行政がそのような「支援」に慣れてしまった理由には、「支援」を求め続ける芸術家たちにも責任がある。芸術家は専門家でなくても「支援」は受けられる。しかし本来、芸術家は専門家であるべきであって、芸術の専門家であるからこそ、行政による支援ではなく「政策」の対象となり得るのではないだろうか。
文化政策のひとつとして舞台芸術を行政が位置づけるためには、公立劇場を地域市民のものであると同時に、世界市民のためのものとして捉えることが必要となる。金森は、劇場の活動を「市民のためのもの」と限定することに、二つの危険性を指摘する。ひとつは、税金によって運営されている公立劇場に、特定の少数の人しかアクセスしなければ、それは地域の文化施設としてふさわしくない。そこで金森は、専属舞踊団があることのメリットとして、地域の教育委員会と行政が連携して、公立の教育機関は必ず鑑賞授業をする制度を設けることで、公立劇場を町の劇場文化の中核として育成することができると主張する。1)地域の学校に鑑賞教室を設ける制度は、長年、宮城聰芸術総監督のもとで静岡県舞台芸術センター(SPAC)が行っており、子どもたちが生の舞台芸術に触れながら育っていく環境を静岡県の公立学校を地盤として育成してきた。SPACは初代の鈴木忠志芸術総監督以来、地域と世界を(東京のような都市を経由せずに)傑出した舞台芸術の水準において直結するという意味において、日本における「公立劇場」のモデルであり続けている。
ふたつめの危険性として、金森は公立劇場における舞台芸術の水準が、テレビで顔を知っていたり、東京の舞台で活躍している俳優の知名度によって質を判断する市民の常識に左右されてしまうことを挙げる。地域において「我々が世界と勝負している」とは、舞台芸術の質的水準において、地域と世界とで同じく水準の高いものであるという意味なのだ。金森は公立劇場になぜ専属の芸術集団が必要なのかについて、次のように述べる――
世界から招聘を受けるような一流の舞台芸術の世界初演を、どこよりも安い値段で、世界で一番に観られる。ワークショップなどを通じて、その専門的身体知を学ぶこともできる。海外の人々が感動しているものを、自分の住む街で体験できること。自分が世界とアクセスできているというリアリティ、「ああ、この感動を地球の裏側の人も味わったんだ」と思えることで開かれる感性やイマジネーション。それは世界的活動を展開する劇場専属集団を抱えることでしか得られない価値である。(同書、65頁)
註
| 1. | ↑ | 地域の学校に鑑賞教室を設ける制度は、長年、宮城聰芸術総監督のもとで静岡県舞台芸術センター(SPAC)が行っており、子どもたちが生の舞台芸術に触れながら育っていく環境を静岡県の公立学校を地盤として育成してきた。SPACは初代の鈴木忠志芸術総監督以来、地域と世界を(東京のような都市を経由せずに)傑出した舞台芸術の水準において直結するという意味において、日本における「公立劇場」のモデルであり続けている。 |

